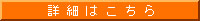出版社 / 著者からの内容紹介
われわれの考えている常識的な幽霊は、昔の日本人の実際生活において見聞したものとはだいぶへだたりがあって、ある傾きを生じたものが、その方向に向かって、民俗生活を置き去りにして独走してしまったのだ日本のゆうれいはなぜ夏に活躍するのか? 幽霊と妖怪の違いとは? 『古事記』から『源氏物語』、歌舞伎芝居に世間話。日本に伝わるさまざまな「ゆうれい話」を通して日本人の集団感覚について考察し、霊魂信仰の本質を明かす「生活史のなかのフォークロア」。中公文庫版に字句の訂正、本文の補訂をおこなった新版。巻末索引を付す。 〈解説・堤邦彦(京都精華大学教授)〉
内容(「BOOK」データベースより)
われわれの考えている常識的な幽霊は、昔の日本人の実際生活において見聞したものとはだいぶへだたりがあって、ある傾きを生じたものが、その方向に向かって、民俗生活を置き去りにして独走してしまったのだ―『古事記』から『源氏物語』、歌舞伎芝居に世間話。日本に伝わるさまざまな「ゆうれい話」を通して日本人の集団感覚について考察し、霊魂信仰の本質を明かす「生活史のなかのフォークロア」。巻末索引を付す。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
池田 弥三郎
1914(大正3)年東京生まれ。慶応義塾大学経済学部予科に入り、のち文学部国文学科に転科、はじめて折口信夫の講義を受ける。国文学科卒業後大学院に進み、以後折口没年まで、塾中等部などの教壇に立ちつつ講義を受ける。41(昭和16)年応召、46年1月帰還。NHK解説委員、国語審議会委員などのほか横綱審議会委員をつとめる。61年文学部教授となる。80年3月退任して、慶応義塾大学名誉教授、洗足学園魚津短期大学教授となる。82年7月没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
1914(大正3)年東京生まれ。慶応義塾大学経済学部予科に入り、のち文学部国文学科に転科、はじめて折口信夫の講義を受ける。国文学科卒業後大学院に進み、以後折口没年まで、塾中等部などの教壇に立ちつつ講義を受ける。41(昭和16)年応召、46年1月帰還。NHK解説委員、国語審議会委員などのほか横綱審議会委員をつとめる。61年文学部教授となる。80年3月退任して、慶応義塾大学名誉教授、洗足学園魚津短期大学教授となる。82年7月没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)