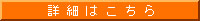Amazon.co.jp
怪談話や都市伝説の背後に見え隠れする歴史的事実を調べ、その由来や変遷を明らかにすることで「怪奇探偵」の異名をとる著者。明治の「妖怪学者」井上円了や、「念写実験」で有名な福来友吉といった研究者の著書、あるいは新聞・雑誌 に至るさまざまな文献を渉猟しながら、日本で最初に写真撮影が行われた幕末から現代までの約120年間を、心霊写真を軸に構築していく「日本心霊写真史」である。
に至るさまざまな文献を渉猟しながら、日本で最初に写真撮影が行われた幕末から現代までの約120年間を、心霊写真を軸に構築していく「日本心霊写真史」である。
その意図するところは、現像ミスやトリックであることが「明治十年代には、日本でもすっかり正体が判明していた」にもかかわらず、なおも現代まで生き続ける心霊写真に、「日本人の精神的な特徴」を見いだすことができる点だ。日本最古の心霊写真が撮影された時期や、「心霊写真」という言葉が初めて使用された時代を特定していく姿勢は、常に冷静である。ただ、「写真の投稿」「鑑定」「供養(処分)」といったシステムが登場した昭和末期から、メディアによる「いい加減な」心霊写真の扱われ方には、「いかがわしさすら失った」と憤りをにじませている点が印象深い。
本書が、福来など戦前の研究者たちの記述に多くのページが割かれているのは、たとえその研究や言動がいかがわしいものであっても、そこに彼らの真摯なまでの情熱を感じているからだ。心霊写真に振り回された人々に向けられる著者の視線には、彼らに対する深い慈しみがある。著者もまた、「古きよき時代」の情熱を継承するひとりなのだろう。(中島正敏)
内容(「BOOK」データベースより)
写ったのは本物か否か…。明治の写真師が、日本初の「心霊写真」を撮影した歴史的瞬間から、現代人が、家庭用ビデオの映像に幽霊を発見するまでの120年史。フィルムに焼き付けられた「幽霊」と日本人の摩訶不思議な関係を辿る。
内容(「MARC」データベースより)
写ったのは本物か否か…。明治の写真師が、日本初の「心霊写真」を撮影した歴史的瞬間から、現代人が、家庭用ビデオの映像に幽霊を発見するまでの120年史。〈ソフトカバー〉